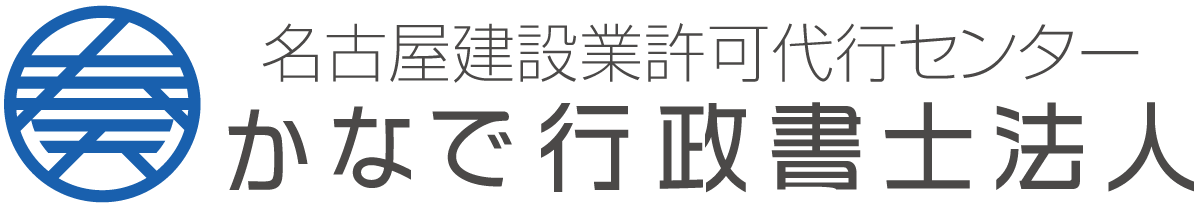建設業許可を取得するためには、以下の要件を備えている必要があります。
また、一般建設業と特定建設業では、要件が異なりますので注意してください。
【要件1-1】経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
建設業許可を取得するに当たって、クリアするのが難しい要件の1つが、この「経営業務の管理」についてです。
令和2年10月に大きな改正がありました。法人では、常勤の役員のうち1人が、個人事業主では、本人か支配人が以下のいずれかに該当することが必要です。
近年では、事業継承やM&A等に対応するためか、複雑な要件が増えましたが、通常ではイの(1)「建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」を用いて申請します。
1.適正な経営体制について
次のいずれかに該当するものであること。
(建設業法施行規則第7条第1号)
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(建設業の財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限
る。)としての経験を有する者
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
経管の証明資料
経営業務の管理責任者になるためには、経営経験を証明できる資料を提出することが必要です。
建設業許可を取得している業者での役員経験がある場合は比較的容易なのですが、完全な許可なしの業者での経験(新規申請等)では、証明資料を提出することにより経営経験を証明します。
具体的には、工事請負契約書や注文書+注文請書または請求書+入金明細等によって証明します。
新規申請は、過去の実績の証明資料集めが必要になります。
【要件1-2】社会保険に加入していること
令和2年10月の改正より、健康保険・厚生年金・雇用保険等の適切な社会保険に加入していることが要件となりました。以前より、国交省が社会保険の加入を促進していましたが、この度の改正により許可を取得するために加入が必須となりました。
尚、常勤役員等(旧:経管)や営業所技術者(旧:専任技術者)全員が他社からの出向である場合などは、申請会社自体が社会保険に加入していなくても建設業許可を受けることができる場合も有ります。
【要件2】営業所技術者(旧:専任技術者)が営業所ごとにいること
令和6年12月13日に施工された改正建設業法により、従来の「専任技術者」が「営業所技術者」という呼称に変更されました。
そして、この「営業所技術者(旧:専任技術者)」についても、難しい要件となっています。
許可を受けようとする業種の工事について下記のいずれかに該当する専任の技術者がいることが要件となります。
現実的に、一般建設業許可では、実務経験10年または資格(施工管理技士等)の要件で申請することが多いです。建築系や工業系など、関連する学科を卒業している方については、実務経験を3年や5年に短縮できる場合もあります。
一方、特定建設業許可の場合は、一級施工管理技士等の資格にて申請することが多いです。
一般建設業の許可の場合
許可を受けようとする業種の工事について
イ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校(所定学科)卒業後5年以上、大学若しくは高等専門学校(所定学科)卒業後3年以上の実務経験を有する方
ロ 10年以上の実務経験を有する方
ハ イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方
(二級建築士、二級土木施工管理技士等)特定建設業許可の場合
許可を受けようとする業種の工事について
イ 国土交通大臣が定めるものにかかる試験に合格したもの、又は免許を受けた方(一級建築士、一級土木施工管理技士等)
ロ 法第7条第2号(左記イ、ロ、ハ)のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方
※ ただし、指定建設業(土、建、電、管、鋼、ほ、園)については、イに該当する方又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方に限ります。
【要件3】請負契約に関して誠実性があること
法人、法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人(申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合)が左に該当すること
この要件に関しては、特に問題になることはありません。
【要件4】財産的基礎または金銭的信用を有していること
請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
建設業許可を取得するためには、財産的基礎があることが必要になります。
一般建設業許可で使われることが多いのは、「直近決算の純資産合計が500万円以上」または、「500万円以上の残高証明書を提出」というパターンです。設立直後の会社であれば、「資本金500万円以上で決算未到来」という方法もあります。
一般建設業許可の場合
下記のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること
イ 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
ロ 500万円以上の資金調達能力のあること
ハ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること特定建設業の場合
申請日の直前の決算において、下記のイ、ロ、ハの要件すべてに該当すること
イ 欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと
ロ 流動比率が75パーセント以上であること
ハ 資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上であること
※なお、経営再建中の方については、更新に限り、特例措置を受けることができます※ 「自己資本」とは、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。
財産的基礎の要件は、主に下記の3パターン
1.直近決算の純資産合計が500万円以上
2.500万円以上の残高証明書を提出(申請受付1ヶ月以内のもの:愛知県の場合)
3.設立直後の会社であれば、資本金500万円以上で決算未到来
【要件5】欠格要件に該当しないこと
法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する方)が次のA~Fの欠格要件に該当するときは、建設業許可を受けることができません。
A 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方
B 不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方
C 不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過しない方
D 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方(法人、個人事業主のみ該当)
E 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
F 次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
・禁固以上の刑に処せられた方
・建設業法に違反して罰金の刑に処せられた方
・建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金の刑に処せられた方
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられた方
建設業許可の要件まとめ
上記1~5の要件が備わっていれば、建設業許可を取得できます。
経営経験の期間が足りていない場合など、待つ以外の方法がないこともありますが、他社経験の資料がもらえなかったり、証明が受けれないなどについては、他の対応策がある場合もありますので、諦めずにぜひご相談ください。